1. はじめに
刑法の因果関係に関する論点の中で、「危険の現実化」説 は現在の主流とされています。しかし、受験答案ではこの概念をうまく説明できず、表面的な言葉の羅列に留まるものが多く見られます。
また、「相当因果関係説と危険の現実化説の違いは?」と尋ねても、正しく説明できる人は意外と少ないのが現状です。本記事では、両説の対比と、近年の判例における因果関係の判断基準 を解説します。
2. 相当因果関係説とは?
① 誕生の背景と意義
従来の「条件説」(「あれなければこれなし」)では因果関係の範囲が広がりすぎるため、それを制限するために生まれたのが 相当因果関係説 です。
特に、事前に予測できない結果が生じた場合に、行為者の責任をどこまで認めるかが問題となりました。そのため、この説では 「行為時に何を考慮するか?」 に重点を置いています。
② 見解の対立
相当因果関係説の中でも、以下のような立場が対立していました。
-
折衷的相当因果関係説(通説)
- 行為時の事情を考慮して因果関係の有無を判断
- 例:「米兵ひき逃げ事件」「梅毒事件」
-
客観的相当因果関係説
- 行為時の事情を厳密に制限し、主観的要素を排除
- 例:「大阪南港事件」(行為後の第三者の介入に対する説明が難しい)
特に、「大阪南港事件」の判例解説では 「行為後の事情を考慮するか?」 という点が問題視され、この説の限界が指摘されました。この議論が、後に 「相当因果関係説の危機」 と言われるようになります。
3. 「危険の現実化説」への移行
① 近年の判例の傾向
平成10年代以降、「相当因果関係説では説明が困難な事例」が増えたことで、新たな判断基準が求められるようになりました。
代表的な判例:
- 「高速道路侵入事件」
- 「夜間潜水事件」
- 「トランク衝突事件」
これらの判例では、「行為後の事情」(第三者の介入や被害者の行動) を考慮し、因果関係を判断する枠組みが採用されました。
② 「危険の現実化説」の確立
平成20年代には、「日航機ニアミス事件」の判決文に 「危険性が現実化した」 という文言が登場し、判例がこの立場に移行したことが明確になりました。
この説の特徴は:
- 行為後の事情(第三者の介入、被害者の行動)をどう考慮するかに重点を置く
- 「相当因果関係説」と明確に対立するのではなく、補完する関係にある
4. 司法試験での答案への活かし方
① 単なるキーワードの羅列を避ける
「危険の現実化説」を単に使うだけでは不十分で、事案に即して因果関係を具体的に説明する必要があります。
② 時代の流れを意識した整理
司法試験の問題では、判例の流れを理解していないと適切に論じられません。特に、過去の判例(平成10~20年代)を踏まえた整理が求められることが多いため、因果関係の判断基準がどのように変遷してきたのかを押さえておきましょう。
5. まとめ
- 相当因果関係説 は「行為時の考慮事情」に重点を置く
- 危険の現実化説 は「行為後の事情」の判断に重点を置く
- 近年の判例は「危険の現実化説」を採用
- 両者は対立するのではなく、補完的な関係
司法試験の論文試験では、単に「危険の現実化」と書くだけでなく、事案のどの部分が「行為後の事情」として問題になるのかを明確に意識することが重要です。

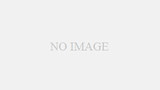

コメント